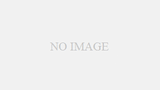現実と仮想の境界が曖昧になる瞬間て、ある気がする。そんな世界を描いているのがNHKアニメの電脳コイル。放送当時はまだスマホも一般的ではなかったその当時に「時代を先取りしすぎた」すごいアニメ。
近未来的な設定でありながらも街並みは昭和感があり駄菓子屋なんかもある不思議な世界観。
ざくっとあらすじ
【AR(拡張現実)技術を利用したメガネ型のウェアラブルコンピュータ、「電脳メガネ」が全世界に普及して11年。
メガネを通して電脳世界の情報を現実世界に重ねて表示され操作ができる。インターネットはもちろん、通話も電脳メガネ1つで事足りる。
電脳技術を使ったペットや道具が存在、子ども達は「メガネ遊び」にハマっている。
小此木優子(オコノギ ユウコ):通称ヤサコは小学校最期の夏休みを目前に、県庁所在地の金沢市から古い街ながらも最新の電脳インフラを備える大黒市に越してきた。
新しい学校で個性豊かな子ども達と出会い、電脳空間で次々に起こる不思議な出来事を体験していく。】
放送時期
2007年5月12日より、NHK教育テレビジョンで放送。全26話。
個人的感想
近未来を描いた技術と現実の境界
2007年はちょうどアメリカでiPhoneが発売されたのです。日本ではBlackBerryとかいうボタンがポチポチとついているスマホ初期型みたいなのを持っている人が少しいたくらいの時代です。
ARなんてまだ微塵もなかった時代に最先端を取り入れた15年以上も前の作品ですが、電脳コイルは「AR」や「デジタルアイテムの共有」などを精密に描いているのです。
人それぞれに評価はありますが、全体的に評価が高い名作です。近い将来、この電脳メガネみたいなものも出来上がりそう。
電脳空間のバグやデータの幽霊。
”見える人”と”見えない人”の世界のズレ。
今電脳コイルを観ると、これってもう現実に起きてるようなことだと感じる瞬間が多々ある。テクノロジーの進化がもたらす”もうひとつの現実”をいち早く描いたアニメなのです。
曖昧な世界とホンモノ
NHK教育テレビ、午後6時半から放送されていたようですが子ども向けではない。と思う。
「電脳コイル」で検索をかけると関連検索ワードに「電脳コイル 『トラウマ』『怖い』」とか出てきます。沢山の子ども達にトラウマを植え付けた作品です。
専門用語も出てきますが説明らしい説明はなく、電脳世界に関する設定をなんとか掴んでいくようなスタイルで、色んな設定を細かく把握していかないといけません。
メガバアのような強烈なキャラクターがいて、メタタグや暗号屋の技に電脳喧嘩。ストーリーは小学生目線で、ちょいちょい笑っちゃうような日常的な話を盛り込みながらオムニバス形式で進行します。しかし電脳世界でまさかのホラー風味がプラスされ、そのあたりがトラウマ要素となったようです。
さらに、後半に近づくほどシリアスになっていくのです。こんなに重い話になるとは思っていなかったので、気になるがもう止まらない。日常の話の中で色んな伏線を散りばめつつ、それらが回収されていく後半は連続再生必至です。
ストーリー中の都市伝説も絡んでいって、見事に電脳世界と融合していて現実との境界が曖昧になっている。「あっち」の世界やミチコさん、4423、ヤサコが出会ったイリーガル。などなど、どんどん繋がっていく面白さです。
そして泣かせてくる。デンスケとおじじは反則です。泣くに決まってました。
電脳空間で「消える」ことは本当の死ではないけど「記憶」は消えない。電脳の世界であっても、本人にはリアルで胸の痛みは確かにあって。だからニセモノではないはずなのに。ホンモノってなんだろう。小学生でこんなに深いことを考えるんです。
技術によって”死”の概念すら曖昧になる。哲学的なテーマがこの作品をただのSFでは終わらせない。
今だから観たい「電脳コイル」
現代はスマホもSNS、AIも日常に溶け込んでいる時代です。メガネ型のウェアラブルコンピュータはまだ存在していませんが、もう似たような世界なのかも。
実際、私個人はこの作品を最近観ました。現代と比べてもなんの違和感もなく観られました。
〆る
笑えて泣けて考えさせられる作品でした。「ジブリ風攻殻機動隊」という意見を見たのですが、なるほどです。